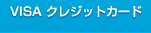新着ニュース30件
2016年11月30日 13:00
2019年度までに
日本の財務省は11月24日に開いた関税・外国為替等審議会で、途上国の輸入関税の税率を低くし、経済発展を支援する「特恵関税制度」を見直し、中国、ブラジル、メキシコ、タイ、マレーシアの5カ国を対象から除外する方針を固めた。この方針は、与党の税制調査会が12月8日にもとりまとめる来年度の税制改正大綱に盛り込まれ、近く政省令が改定される見通しである。財務省は、制度見直しの開始まで2年間の経過期間を置き、2019年度までに新たな適用基準が適用、上記5カ国が対象から除外となる予定である。
「特恵関税制度」
「特恵関税制度」は、途上国の輸出振興や経済支援を目的に、関税引き下げや免除を行う制度である。多くの先進国が導入しており、日本も143カ国・地域からの輸入品を対象に、関税を減免している。その一方で、中国など5カ国は、急速な経済発展で輸出競争力が上昇、援助の必要性が薄れており、欧州連合(EU)やカナダはすでに同様の制度の対象から外している。日本も一定の見直しが必要と判断した模様だ。
現在、特恵関税制度は3年連続で高所得だった国および地域を対象から除外している。日本はここに新たに「高中所得国に分類され、かつ輸出の世界シェアが1%以上」という基準を設けて適用する予定だ。新たな基準によれば、前述の5カ国が特恵関税除外の対象となる。
特恵関税除外の効果と影響
現在、特恵関税対象になっているのは、日本の輸入額の約2%(1兆6,000億円分)にあたる。特恵関税で失われている関税収入は330億円で、このうち適用対象から外される5カ国で300億円を占めている。5カ国が適用除外されれば、これだけ関税収入が増える可能性が高く、日本は税収増が期待できる。
ただ、トランプ次期米大統領が中国やメキシコからの輸入品に高関税をかけると訴えてきたことなどもあり、「日本の制度変更は実質的な関税引き上げ」との誤解を招く恐れがある。財務省は今回の改定の意図を丁寧に説明する必要がある。
また、特に中国では、多くの日本企業が拠点を構え、現行の関税を前提にしてグローバルな生産・流通体制を築いてきているため、中国から原料を輸入する日本企業の拠点配置や、輸入品の値上がりなどの影響がでる可能性があると指摘されている。
財務省 関税・外国為替等審議会 関税分科会
http://www.mof.go.jp/
-->
記事検索
アクセスランキング トップ10
特集
お問い合わせ